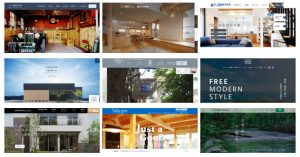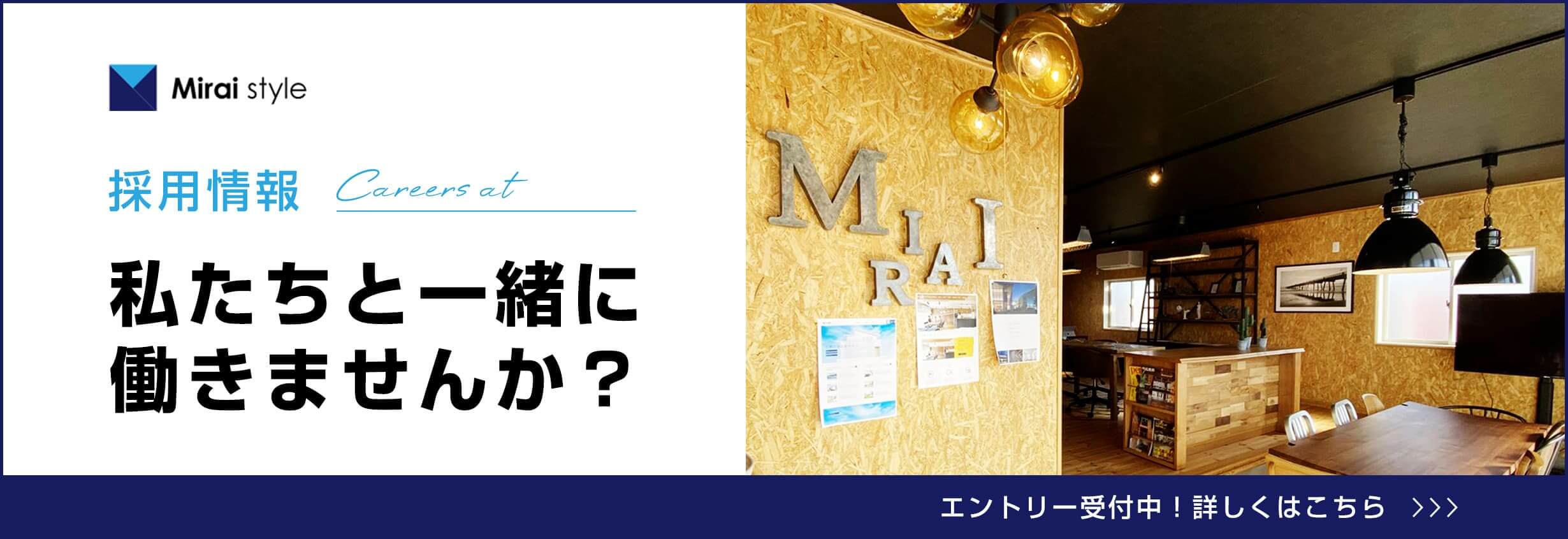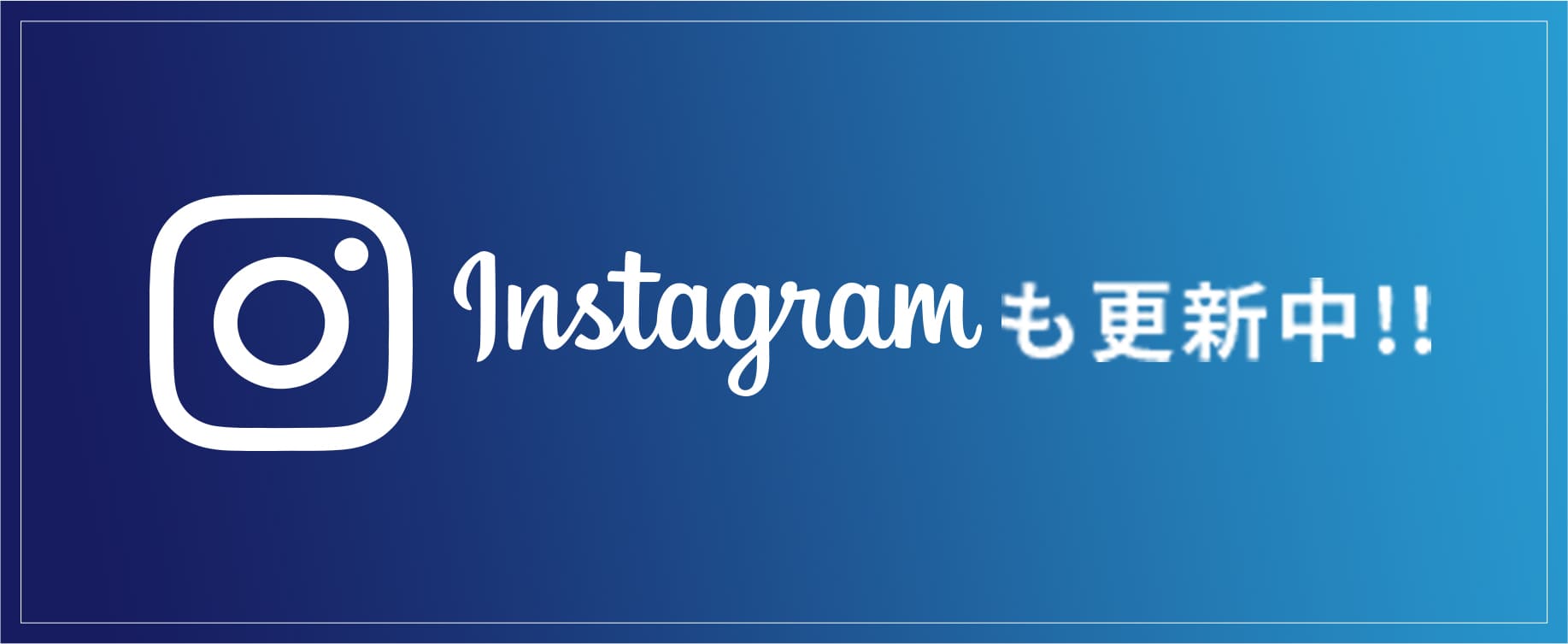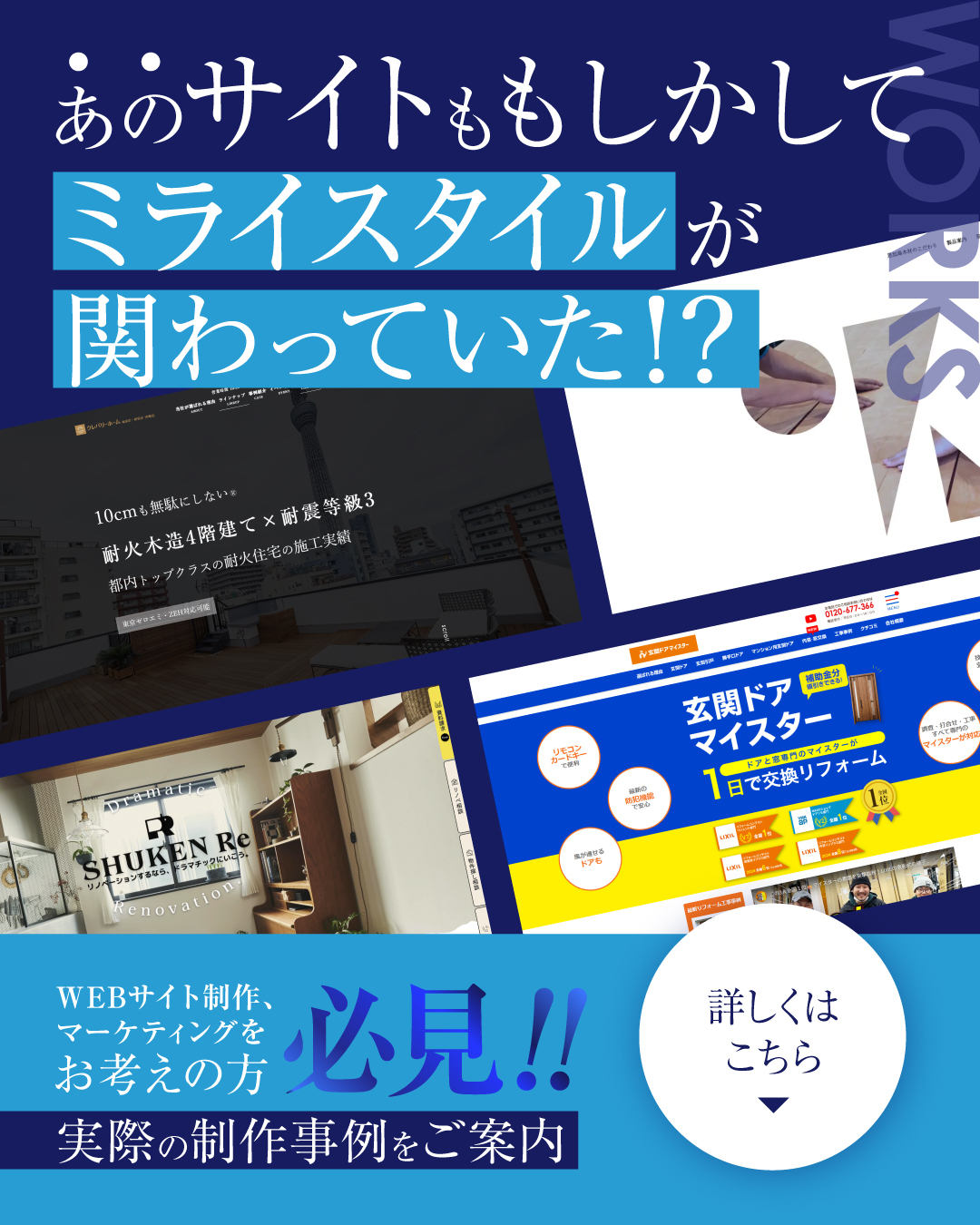建築士は仕事がなくなる・食えないと言われる理由|将来の建築士の需要・必要なスキルを解説
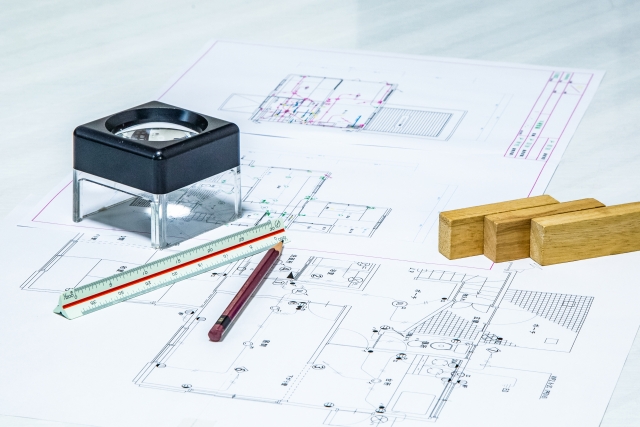
「建築士の仕事は将来なくなる」「一級建築士でも食えない」そんな声を耳にすることがあります。
AIやBIMの進化、人口減少による建築需要の変化など、業界を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。
しかし実際には、建築士という職業がなくなるわけではありません。
時代に合わせてスキルや働き方をアップデートすれば、今後も十分に活躍できる可能性があります。
この記事では、一級建築士が「仕事がなくなる」と言われる背景や将来の需要、AI時代に求められるスキルをわかりやすく解説します。
ミライスタイルでは、建築業界に特化したホームページ制作や運用を行っています。
建築士や設計事務所の強みを正しく伝え「選ばれる仕組み」を作るお手伝いをしています。
集客に課題を感じている方は、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。
目次
一級建築士は仕事がなくなる・食えないと言われる理由

近年、AIやBIMなどの技術発展や建築需要の変化により、「建築士は将来なくなる」と不安視する声もあります。
しかし実際には、業務の一部が効率化されるだけで、建築士の役割そのものが消えるわけではありません。
ここでは、建築士が「仕事がなくなる」「食えない」と言われる理由を解説します。
AIの普及による設計業務の効率化
建築業界ではBIM(Building Information Modeling)やAI設計支援ツールの導入が進み、設計業務の効率化が加速しています。
BIMを活用すれば、図面作成や構造・設備の整合性チェック、数量拾い出しといった作業を一元的に管理でき、手作業によるミスや修正作業を大幅に削減できます。
また、AIによる設計支援では、建物の日照・風通し・動線シミュレーション、コストやエネルギー消費量の自動算出なども可能になり、初期段階から高精度な設計検討が行えるようになりました。
従来は人手と時間を要していた業務が自動化されることで、「建築士の仕事がAIに奪われるのでは」と感じる人が増えたことが、仕事がなくなると言われる背景の一つです。
建築業界で活用されているAIについては、こちらの記事で確認できます。
【関連ページ】2017年に発表された建築業界のAI活用実例まとめ(18事例)
建築需要の地域格差・人口減少
日本全体で人口減少と住宅ストックの増加が進むなか、新築住宅の着工数は年々減少傾向にあります。
特に地方では、世帯数の減少や空き家の増加により、新築需要が縮小し、リフォームやリノベーションなど既存住宅を活用する工事が中心になりつつあります。
一方、都市部では再開発や大型商業施設の建設、省エネ・防災対応などの案件が増え、地域によって建築士に求められる業務の内容や専門性が大きく異なるのが現状です。
地域によって仕事量や単価の差が広がり、案件を安定して確保できない建築士も少なくありません。
勤務環境・働き方のハードさと報酬抑制
建築士が「食えない」と言われる背景には、以下のような働き方や待遇面での構造的な課題もあります。
- ・長時間労働・休日出勤の常態化
- ・報酬体系の不透明さ・設計料の抑制
- ・将来性・昇進の道筋の不透明さ
建築士は、設計・監理の業務は納期や現場進行と密接に関わるため、残業や休日出勤が避けられない状況になりやすく、プライベートとの両立が難しいという声も多く聞かれます。
また、建築士の報酬は「設計監理料」で支払われますが、実際には建築主や施工側の予算や事情に合わせて調整されることも多く、法定基準より低くなる場合もあります。
評価制度や昇進の仕組みが明確でない職場も多く、努力や成果が収入に反映されにくい環境も課題です。
資格取得後のキャリア格差と待遇の違い
一級建築士の資格を取得しても、勤務先や担当業務によって収入や待遇には大きな差があります。
厚生労働省の「令和6年度賃金構造基本統計調査」によると、建築士の平均年収は約630万円で、平均月収は約40万円、平均ボーナスは約150万円です。
建築士の給与水準は、勤務先の規模にも影響されます。
たとえば、設計事務所勤務では500〜600万円程度、ゼネコン勤務では700万円以上という求人事例も見られ、所属先によって大きく年収水準が異なる傾向です。
〈参照〉厚生労働省ホームページ:令和6年度賃金構造基本統計調査
建築業界全体の高齢化
建築士業界では、資格者の高齢化が深刻化しています。
国土交通省「建築士登録状況(令和7年)」によると、一級建築士の登録者数は約38万人に上りますが、新規登録者数は年々減少しており、若手の参入が追いついていない状況です。
資格取得までに多くの実務経験と勉強時間を要することや、長時間労働・報酬水準の低さから若年層が魅力を感じにくいことが原因とされています。
このため、業界全体の高齢化が進み、将来的に設計・監理業務を担う人材が不足するリスクが指摘されています。
〈参照〉国土交通省ホームページ:一級建築士免許の登録等について
建築業界でホームページ制作や運用を相談したい企業様は、ミライスタイルにお問い合わせください。
技術力だけでなく、「どんな価値を提供できる建築士か」を伝えるサイトづくりで、認知拡大と問い合わせ増加をサポートいたします。
【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。
将来の一級建築士の需要|AIで代替できる業務・できない業務

AIやBIMなどのデジタル技術が急速に発展するなかで、「将来、建築士の仕事はAIに置き換えられるのではないか」と思う方も多くいらっしゃいます。
しかし、法的責任や安全性の判断など、建築士にしか担えない領域も多く、すべてがAIに置き換わるわけではありません。
ここでは、AI時代における一級建築士の需要と、代替可能な業務・不可能な業務について解説します。
一級建築士の仕事はなくならない
建築士の仕事の中心は、建築基準法などの法令を守りながら、安全で快適な空間をつくることです。
AIが設計を支援できるようになっても、最終的な判断や責任を負うのは人間の建築士です。
また、建築物の設計は立地条件、用途、施主の希望など多様な要素を調整しながら進めるため、単純な自動化では対応しきれない部分も多くあります。
そのため、AIの導入が進んでも「建築士の仕事そのものがなくなる」ことはありません。
AIが代替できる一級建築士の業務
AIの導入により、設計や監理における定型的な業務は効率化が進んでいます。
AIが代替できる主な業務は以下のとおりです。
- ・図面の自動生成
- ・BIMによる3Dモデリング
- ・法規チェックの自動化
- ・パース・CGの作成
- ・日照・風通し・採光シミュレーション など
これらの作業は膨大なデータ処理や計算を伴うため、AIやBIMツールの得意分野です。
従来は人手と時間を要していた作業も、AIを活用することで短時間かつ高精度に実行できます。
BIMの概要については、こちらの記事を参考にしてください。
【関連ページ】建築業界の新たな常識「BIM」をわかりやすく解説|メリット・デメリットやCADとの違い
AIが代替できない一級建築士の業務
AIでは代替できない領域も多く存在します。
- ・施主の要望を引き出すヒアリングや提案
- ・意匠性と機能性を両立するデザイン設計
- ・施工現場との調整や安全確認
- ・地域特性や街並みとの調和
- ・防災・環境配慮 など
建築は、住む人や使う人の想いを形にする仕事であり、感性・経験・コミュニケーション力が大きな役割を果たします。
また、現場では予期せぬ課題への柔軟な対応や、社会的責任を伴う安全性の確認もAIには担えない部分です。
AIが進化しても「人にしかできない判断や提案」が求められる領域は多く残っており、建築士の存在はこれからも必要とされています。
将来の一級建築士に必要な5つのスキル

AIの進展、社会の価値観の変化にともない、建築士に求められるスキルも大きく変わりつつあります。
ここでは、今後の時代を見据えて一級建築士が身につけておきたい5つのスキルを紹介します。
DX・BIM活用スキル
近年、建築業界でも「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の流れが加速しています。
そのため、今後の建築士には、AIやBIMなどのデジタル技術を使いこなす力が欠かせません。
AIに図面作成や数量算出などのルーティン作業を任せることで、建築士はより重要な設計提案や調整業務に集中できるようになります。
また、BIMは設計・施工・管理の情報を一元化し、チーム全体の共有や意思決定をスムーズにする仕組みです。
デジタル技術を取り入れることは、AIに仕事を奪われないためではなく、自分の提案力や判断力を高めるための手段です。
技術を味方につけることで、建築士としての可能性を広げることができます。
工務店・建設会社でDX化する方法は、こちらの記事でも解説しています。
【関連ページ】工務店・建設会社DXの方法|WEB強化で差を付ける!
コミュニケーション・マネジメント力
建築士は図面を描くだけでなく、施主・施工会社・行政など多くの関係者と関わります。
一つの設計には、コスト、デザイン、法規、安全性など多くの視点が関わるため、それぞれの立場や意見を調整し、最適な形にまとめる力が求められます。
また、現場では想定外の課題やトラブルが発生することも珍しくありません。
冷静に状況を整理し、関係者と対話を重ねながら解決策を導く力も重要です。
人と協力し、チームとして成果を出すスキルが今後さらに重要になります。
法規・環境・省エネ対応スキル
これからの建築士には、環境への配慮や省エネルギー性能を踏まえた設計力が重要です。
住宅分野では、ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)や断熱等級の見直しなど、省エネ基準の強化が進んでおり、法律や制度の理解が欠かせません。
建築分野でもSDGsやカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが加速しており、再生可能エネルギーや環境配慮素材の活用など、幅広い知識を身につけておくことが大切です。
社会全体がサステナブルな方向に進む中で、環境や法規に対する理解を深めることは、専門家として信頼される建築士になるための大切な要素です。
リフォーム・リノベーション対応力
人口減少と住宅ストックの増加により、新築よりも既存住宅の改修や再生の需要が高まっています。
これまでのように新しい家を建てるだけでなく、既存の建物を活かしながら暮らしやすさを高める設計が求められる時代です。
リフォームやリノベーションでは、耐震補強や断熱改修、バリアフリー化など、建物の性能を向上させる知識と技術が不可欠です。
同時に、古い建物ならではの味わいや素材を残しながら、新しい価値を生み出すデザインの発想力も重要になります。
建物を「壊して建てる」から「活かしてつくる」へと発想を転換できる力が、これからの建築士には求められます。
専門資格による業務拡張
一級建築士のなかでも、さらに専門性を高めて活躍の幅を広げられるのが、「構造設計一級建築士」と「設備設計一級建築士」です。
どちらも2006年の建築士法改正によって新設された国家資格で、一級建築士としての登録に加え、5年以上の実務経験と所定の講習修了が必要になります。
【構造設計一級建築士の主な特徴】
- ・高層ビルや大規模施設など、建物の構造安全性を専門的に扱う
- ・耐震性や構造強度の検証・設計を担当
- ・高さ60mを超える高層建築や、延べ面積2,000㎡を超える学校・病院などの特定建築物では関与が法律で義務付けられている
【設備設計一級建築士の主な特徴】
- ・建物の空調・電気・給排水などの設備設計を専門的に担当
- ・建物全体の快適性や省エネルギー性能を左右する重要な役割を担う
- ・延べ面積2,000㎡を超える特定建築物(事務所ビル・病院・学校など)では、設計または確認が法律で義務付けられている
専門資格を取得することで、担当できる業務の範囲が広がり、設計報酬の向上やキャリアの安定にもつながります。
専門資格を活かすには、「選ばれる建築士」としての発信力も大切です。
ミライスタイルは、建築業界に特化したホームページ制作や運用支援を通じて、建築士・設計事務所の魅力発信をサポートしています。お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。
一級建築士の将来性Q&A

最後に、一級建築士の将来性について、ミライスタイルがよくいただく質問・回答を紹介します。
一級建築士の平均年収を知りたい
厚生労働省「令和6年度賃金構造基本統計調査」によると、建築士の平均年収はおよそ 630万円前後とされています。
ただし、この数字はあくまで全体平均であり、勤務先の規模や担当業務、独立の有無によって収入は大きく異なります。
一級建築士はスキルや実績が評価に直結する職業であり、経験を重ねることで報酬アップやキャリアの幅を広げることが可能です。
一級建築士資格は希少性がある?
一級建築士は、試験の合格率がおよそ10%前後と低く、取得までに多くの実務経験と専門知識が求められる国家資格です。
建築関連資格の中でも難易度・希少性が高く、企業からの信頼度も高い資格といえます。
今後、AIやDXの進展によって業務内容は変化していきますが、「法的責任を担える設計者」としての価値は変わらず、専門職としての地位は維持されると言えます。
どのような企業に就職できる?
一級建築士は、設計・施工・行政・不動産と幅広い分野で活躍できる資格です。
主な就職先は以下の通りです。
- ・設計事務所(意匠・構造・設備設計)
- ・ゼネコン・建設会社(設計・施工管理・技術部門)
- ・ハウスメーカー・工務店(住宅設計・商品開発)
- ・行政機関(建築確認・都市計画などの審査業務)
- ・不動産・デベロッパー(開発企画・設計監修)
一級建築士として独立しても生活できる?
一級建築士として独立する人も多く、設計事務所を立ち上げて個人・法人案件を受けるケースが一般的です。
ただし、開業当初は案件獲得や営業活動が課題になることもあり、安定収入まで時間がかかる場合があります。
リノベーションや住宅設計、商業施設など得意分野を明確にし、強みを打ち出すことで、競合との差別化ができ、長期的に安定した経営につながります。
独立はリスクもありますが、スキルと人脈を活かして自分のペースで働ける点は大きな魅力です。
まとめ|建築士は「なくなる職業」ではなく「進化する職業」

AIやDXの発展により、建築士の仕事は変化しています。
しかし、法的責任を担い、暮らしや社会の基盤をつくるという役割は、これからも人にしかできないものです。
時代に合わせてスキルを磨き、デジタル技術を取り入れることで、建築士の活躍の場は広がっています。
建築士は「なくなる職業」ではなく、社会とともに形を変えながら進化し続ける専門職です。
ミライスタイルは建築業界専門のWEB制作・運用会社です。
建築に特化することで業界のニーズに的確に対応し、集客できるホームページをご提供しています。
設計事務所・設計事務所のサポート事例も数多くございますので、独立や事務所の開業、集客のお悩みなどぜひお気軽にご相談ください。
全国からお申込みいただけるWEB個別診断もございます。
【お問い合わせ】建築業界WEB活用オンライン個別相談を、毎日開催しています。
株式会社ミライスタイル
https://mirai-style.net/
〒300-2417茨城県つくばみらい市富士見が丘2-14-5
tel:029-734-1307
fax:029-734-1308